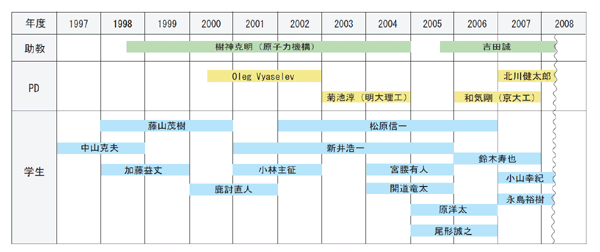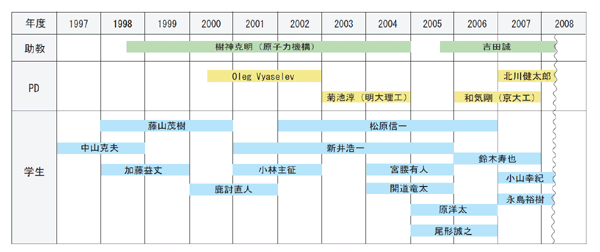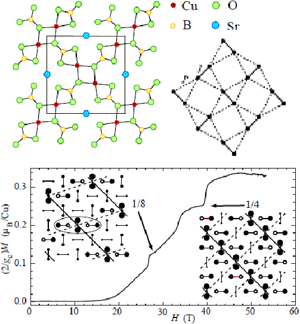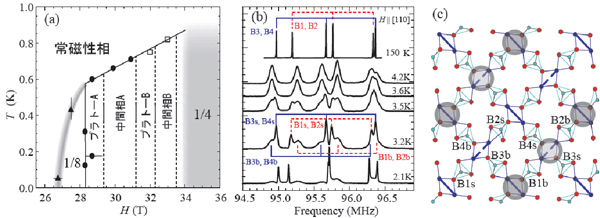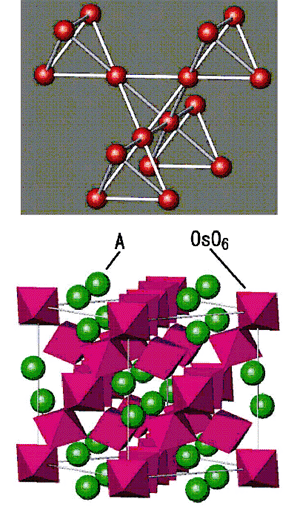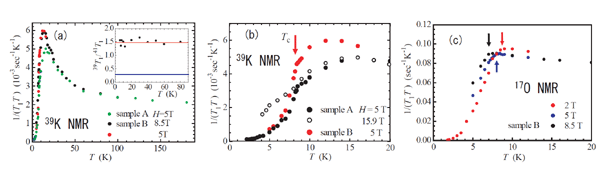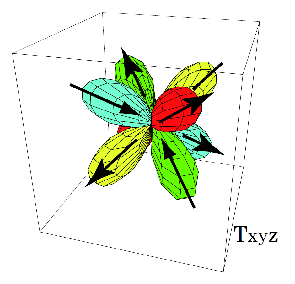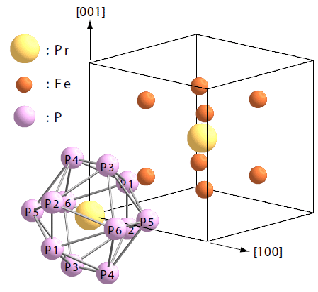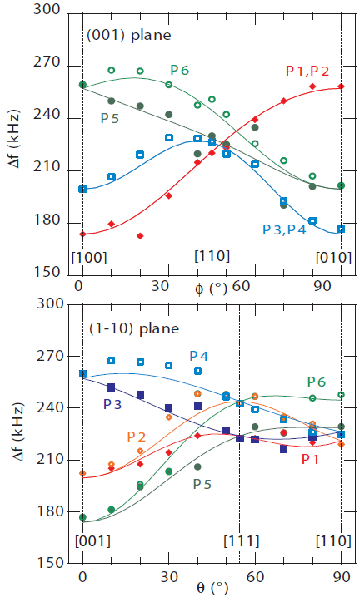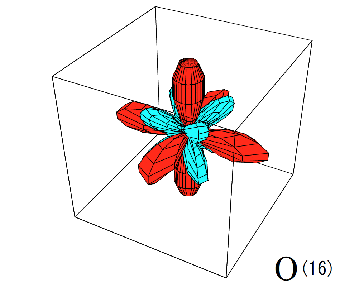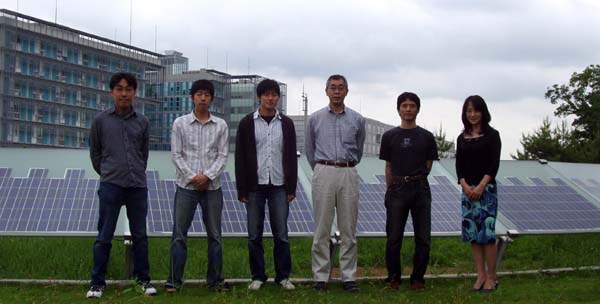~研究室だより~(「物性研だより」より転載)
瀧川研究室
新物質科学研究部門 瀧川仁
1.はじめに
私が物性研に着任して11年が経過した。改めて月日の経つ早さを思い知るが、研究室だよりを書くようにという依頼を受けたのを良い機会に、主として物性研が柏に移転して後の研究室の活動を振り返ってみたい。思い返すと、ちょうど30年前に大学院生として物性研・安岡研究室に入門して以来ずっとNMR(核磁気共鳴)の実験を行ってきた。一時期他の実験手段にも習熟することを考えたが、実現しないまま現在に至っている。しかし今でも新しいテーマに向かう度にNMRの魅力を再発見する。それは一言でいえば、謎解きの面白さということであろうか。
NMRに限らず、一般に分光学的実験手法においては、対象物質に刺激を与えてその応答を周波数、或いは時間の関数として観測する。観測量が単なる一つの平均値ではなく、周波数空間における分布を持った構造として得られる点が、分光実験の魅力である。また、刺激の与え方には多様性があり、実験家が工夫を凝らす余地が生まれる(NMRでは原子核やパルス条件の選び方に相当する)。更に、NMRに特有の利点として、①結晶単位胞内の異なる原子やサイトの振る舞いを分離して観測できること(原子サイト選択性)、②磁気モーメントと電気四重極モーメントを併せ持つ原子核は、磁気的・電気的超微細相互作用を通じて、周囲の電子のスピンや軌道磁気モーメントに由来する磁気的性質のみならず、電子の電荷分布や結晶の局所的構造、格子振動をも含む殆どありとあらゆる物性に対するミクロなプローブとなる、③共鳴スペクトルに現れる静的な情報だけでなく、核磁気緩和時間(T1, T2)の測定からダイナミクスを知ることができる、という点をあげる事が出来る。
NMRの面白さは、研究対象として選んだ物質について明確な情報を得るために、これら多彩な特徴をどのように生かして実験を組み立てるかという計画のプロセスと、得られた結果から背後にある物理現象を解き明かす謎解きのプロセスにある。以下、柏で行ってきた研究結果の幾つかを紹介するが、NMR研究の魅力の一端が読者に伝われば幸せである。下表に、今までの研究室に在籍したメンバーの氏名と在籍期間を記す(カッコ内は現所属先)。また以下に紹介するそれぞれのテーマを担当した方の名前を本文中にカッコで示す。
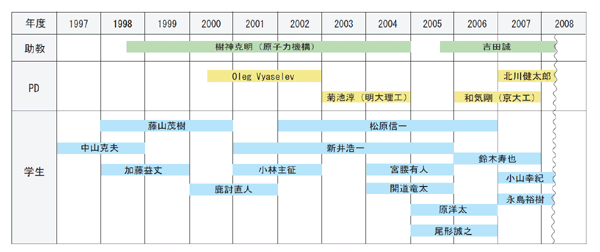
現在までのメンバー
2.フラストレートした量子スピン系
スピン・シングレットを形成する2量体が結晶格子上に並んだ系に、磁場や圧力をかけて誘起される量子相転移が近年興味を呼んでいる。磁場中では2量体のトリプレット励起子(マグノン)はゼーマン分裂を起こし、磁場方向に分極した分岐のエネルギー・ギャップが磁場と共に減少する。磁場はマグノンに対する化学ポテンシャルとして働き、ある臨界磁場以上で励起ギャップが消失すると、有限の磁化(=マグノン密度)が現れると同時にマグノンのボーズ凝縮が起こる。これは元のスピン系の言葉では、磁場に垂直な面内で回転対称性が破れた反強磁性秩序相に対応する。しかし現実の結晶では、異方的な相互作用によって始めからスピンの回転対称性が消失し、ボーズ凝縮の概念が厳密には成立しない場合も多い。また圧力を印加した場合も、2量体間相互作用の増加に伴いマグノンのバンド幅が増大し、やがてギャップが消失する場合がある。更にこのような系に強い磁場をかけて磁化を飽和させる過程で、新奇な秩序相の出現が期待されている。特にフラストレートした格子上ではマグノンの運動エネルギーが抑制され、トリプレット間の反発力のためにマグノンが局在化し超格子が形成される場合がある。これは電子系におけるウィグナー結晶、或いは電荷秩序に似た現象であるが、スピン系の場合は磁化プラトーとして観測される。
結晶の周期性を破るスピン超格子を伴う磁化プラトーの実例は、ごく僅かしか知られていない。最も有名なのはSrCu2(BO3)2で、飽和磁化の1/8, 1/4, 1/3において磁化プラトーを示す[1](図1)。この物質は物性研・上田寛研の助手であった陰山洋氏(現京大)を中心として過去10年の間、活発な研究が続けられている。2002年に私は当時の樹神助手(現原子力機構)と一緒にグルノーブル強磁場施設にて銅サイトのNMRを行い、1/8プラトー領域の27.6テスラの磁場において巨大な単位胞を持つスピン超構造を検証した[2]。この経緯は2002年11月の物性研だより(42巻第4号)に詳述したので、ここではその後の発展について簡単に述べる。
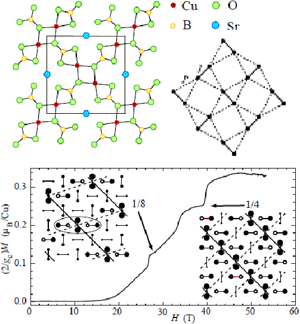
図1 上:SrCu2(BO3)2の結晶構造と直交ダイマー模型。下:磁場をc軸にかけたときの磁化曲線 [1] と1/8、1/4プラトーにおけるスピン超構造。楕円はゼロ点振動により3個のダイマーに広がったトリプレット状態を示す。
2006年に1/8プラトーを越える31テスラまでの定常磁場下でホウ素サイトのNMR測定を行ったところ(松原信一)、1/8プラトー相とほぼ同程度の広がりを持つ内部磁場分布が観測され、プラトーの間の中間相でもトリプレットが局在したスピン超構造が存在していることが分かった[3]。更に今年になって、34テスラまでのNMR測定(和気剛)と32テスラまでの磁化・トルク測定[4]を行い、1/4プラトー相に至る磁気相図の全貌が明らかになった。図2(a)に示すように、1/8プラトーと1/4プラトーの間に二つの新しいプラトー相(恐らく2/15と1/6?)を含む四つの異なる相が存在するという予想外の結果であった。プラトー相と磁化が連続的に変わる中間相は磁化曲線を見れば区別できるが、NMRスペクトル上でも、多数のシャープな共鳴線が分離しているプラトー相と、連続的なバックグラウンドの上にブロードなピークが重なっている中間相は、定性的に明瞭に区別される。磁化が連続的に変化するにも拘わらずスピン超構造が存続している状態は、トリプレットの固体成分とボーズ凝縮成分が共存している超固体相ではないかという期待を抱かせる。しかし、我々の以前のNMRの結果[5]から、ダイマー内のスピン間にはジャロシンスキー・守谷相互作用が働き、c面内のスピンの等方性が破れていることが分かっているので、厳密な意味でのボーズ凝縮は起こらない。高磁場相を理解する上でもDM相互作用の影響は重要であると思われる。今回の実験で、量子ホール効果にも似た精緻な相図がスピン系において見出されたことで、今後理論的な解明が一段と進むことが期待される。
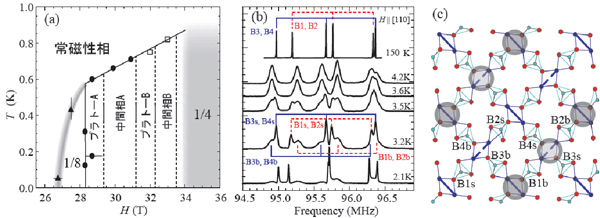
図2 (a) SrCu2(BO3)2における高磁場磁気相図。(b) 2.4GPaの圧力下、7Tの磁場下で観測されたNMR共鳴線の分裂。(c) NMRの結果から推定された高圧における新しいVBS秩序相の模式図。直交する2種類のダイマー副格子が構造相転移によって非等価となり、更にそれぞれの副格子中で、円で囲んだギャップの小さい磁気的ダイマーとギャップの大きい非磁性ダイマーが超周期構造を形成する。図中の記号は非等価なホウ素サイトと、(b)図の分裂した共鳴線の対応関係を示す。
一方、我々はこの物質が圧力下においても不思議な磁気相転移を示すことを見出した(和気剛)[6]。0.3GPa以上の圧力下、c軸方向の磁場下でホウ素核のNMRを行うと、約30Kより低温で共鳴線が徐々に分裂する。スペクトルの磁場方向依存性から、この分裂の原因は直交する二つのダイマー副格子が非等価になったためであることが分かった。(圧力下のX線(物性研・山浦淳一氏)で、実際に4回対称性が消失する構造変化が確認されている。)ところが図2(b)に示したように、2GPa以上の高圧では更に4K以下で全ての共鳴線が分裂し、低温ではシフトが殆どゼロのシャープな共鳴線(図2(b)でB1s-B4sと名づけたライン)と有限のシフトを持つブロードな共鳴線(図2(b)のB1b-B4b)が現れる。これは純粋に磁気的な2次相転移で、2つのダイマー副格子のそれぞれが2倍周期の超構造を形成することを示している。しかし低磁場では、両方の共鳴線とも低温でゼロシフトに近づくので、自発磁化は存在しないと思われる。従ってこの秩序相は図2(c)に示したように、それぞれの副格子上にギャップの異なる2種類のダイマーが自発的に形成された状態で、ダイマー内スピン相関の反強成分が秩序パラメータであると推定される。これは一種のValence-Bond-Solid(VBS)秩序と考えることが出来そうであるが、このような秩序は今まで例がなく、ミクロな機構の解明が待たれる。
スピン1/2を唯一の自由度とする単純な系でありながら、10年を経てなお新奇な量子現象が尽きないこの物質は、量子スピン系の中でも稀有の物質と言ってよいだろう。今後もまだ楽しめそうな物質である。
3.パイロクロア型アルカリ・オスミウム酸化物におけるラットリングの観測
超伝導の話題に移ろう。1987年から1994年にかけて私はもっぱら銅酸化物超伝導体の実験に携わっていたが、その後興味が主にスピン系に移っていった。ところが近年物性研の廣井研究室でパイロクロア格子上の新しい超伝導酸化物が発見され、再び超伝導に関わる機会を得た。A2B2O7の組成式を持つパイロクロア化合物の中ではフラストレーションの強い磁性体が多数知られているが、超伝導体は長い間見つかっていなかった。(同じパイロクロア格子を含むスピネル化合物ではLiTi2O4という超伝導体が知られている。)ところが2001年にCd2Re2O7が転移温度1Kの超伝導体であることが、廣井研(花輪氏ら)と京大の吉村研で同時に独立に発見された[7]。我々は(Oleg Vyaselev、新井浩一、小林主征)廣井研で合成された単結晶を用いて、CdサイトのNMRやReサイトのゼロ磁場下NQR(核四重極共鳴)を行った。Reサイトの核磁気緩和率は、超伝導転移温度直下で巨大なコヒーレンスピークを、低温では活性化型温度依存性を示し、典型的な弱結合BSC超伝導体であることが分かった[8]。超伝導に関する興味は薄れたが、200Kと120Kで起きる逐次構造相転移と電子物性の関連が注目された。これに関しても、NMR/NQRで観測されたサイト対称性の低下から各相の可能な空間群が絞り込まれ、後の構造解析を進める上での指針となった[8,9]。しかし、反転対称性の僅かな破れを伴う構造相転移が物性にどのような影響を及ぼしているかという点は、今でもあまり良く分かっておらず、まだ今後の進展が期待される。
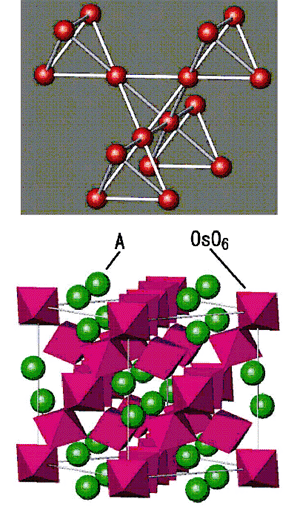
図3 パイロクロア格子(上)とAOs2O6の結晶構造(下)。
その後2004年に廣井研(米澤氏ら)でまた新しい超伝導体が発見された[10]。ベータ・パイロクロア型と名づけられたAOs2O6 (A=K, Rb, Cs)の組成式を持つこの系は、通常の227組成のパイロクロア化合物において、遷移金属サイトが形成するパイロクロア副格子を保持し、もう一つのパイロクロア副格子の正四面体の中心をアルカリイオンで置き換えた構造を持つ(図3)。アルカリ元素によって転移温度が9K(K), 6K(Rb),3K(Cs)と大きく変化し、最も高いTcをもつK化合物において、比熱や電気抵抗の異常な振る舞いが観測されたことから、超伝導研究者の大きな興味を引いた。我々も(新井浩一、吉田誠)超伝導の発見直後からKOs2O6とRbOs2O6について、アルカリ原子サイトのNMRを開始した。
図4(a)(b)にKOs2O6における39K核の核磁気緩和率(1/T1)を温度で割った量を示す。金属における核磁気緩和機構としては、通常スピン反転を伴う伝導電子の散乱(コリンガ過程)が支配的で、1/(T1T)は温度によらず一定となる。しかし実験データは(試料依存性があるものの)これとは異なり、温度を下げると1/(T1T)が増大し、13K付近でブロードなピークを示した後に緩やかな減少に転じ、更に超伝導転移温度以下で急激に減少する。一方、87Rb核ではこのような異常は見られなかった。磁化率がほぼ温度に依存しないパウリ常磁性を示すにも拘わらず、1/(T1T)が低温で増大することは、一般に低エネルギーの反強磁性的スピン揺らぎの発達を意味する。また13K以下の減少は、銅酸化物高温超伝導体のアンダードープ領域で見られた擬ギャップ現象と酷似している。我々は、このような特異な反強磁性的スピン揺らぎが最高のTcを示すK化合物でのみ観測されたことを強調して論文を投稿した。2人のレフェリーからはいずれも好意的なコメントが送られ、多少手直しをして再投稿すれば出版されるはずであった。ところが私の悪い癖で、改訂をさぼって論文を暫く放置しているうちに状況が変わってきた。
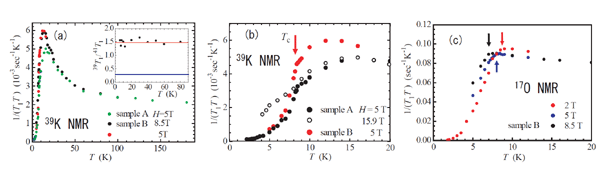
図4 (a) KOs2O6における39K核の1/(T1T)の温度依存性。挿入図は39Kと41Kの緩和率の同位体比。赤線、青線はそれぞれ四重極モーメントと磁気モーメントの二乗比を表す。(b) 同じデータの低温部分の拡大。(c) KOs2O6における酸素サイトの1/(T1T)の温度依存性。矢印はそれぞれの磁場における超伝導転移温度を示す。
この物質では、オスミウムと酸素が作る籠状の広い空間の中心にアルカリイオンが比較的孤立して存在する。その頃、同じような籠状構造を持つ他の物質において、ラットリングと呼ばれる籠中原子の非調和振動が観測され、異常な熱的・弾性的性質の原因であると考えられるようになってきた。そしてベータ・パイロクロア系においても、アルカリイオンのラットリングの可能性が指摘され始めてきた。一般に、格子振動は原子核位置の電場勾配に時間的な変調を加えるので、電気四重極相互作用を通じて核磁気緩和の原因となり得る。しかし、これまで知られている金属ではいずれも磁気的な緩和機構が圧倒的に優勢で、フォノンによる緩和の観測例は、他に緩和の原因となるものがない非磁性絶縁体イオン結晶に限られていた。我々も当初はフォノンによる核磁気緩和など考えもしなかったのだが、ラットリングが議論され始めるに及んで、念のため緩和機構を実験的に確かめておこうと考えた。カリウムには3/2の核スピンを持つ二つの同位体39Kと 41Kがあり、39Kがより大きな磁気モーメントを持つが、電気四重極モーメントは41Kの方が大きい。従って両者の1/T1 の値を比較すれば、どちらの緩和機構が支配的なのか実験的に決定できる。同位体比を測定してみると、驚いたことに測定した全温度域でほぼ100%フォノンによる緩和であることが分かった(図4(a)の挿入図)。とすると、超伝導転移温度以下で緩和率が急激に減少するのは、超伝導によって電子励起にギャップが開いたためではなく、電子格子相互作用を通じてフォノンの動的特性が超伝導により変化したためと考えなくてはいけない。一方、電子系のスピン励起に関する情報は、籠を形成するオスミウムまたは酸素サイトのNMRに反映されるはずである。実際に17O同位体を含む試料に対し酸素サイトの緩和率を測定すると、1/(T1T)はTc以上でほぼ一定で低温で急激に減少し、カリウムサイトとは全く異なる温度変化が観測された(図4(c))。しかも転移温度直下での変化はなだらかで、通常の超伝導体で期待されるコヒーレンスピークが抑制されているように見える。この原因としては、超伝導準粒子がラットリングによる強い散乱を受けていることが考えられる。このように、測定する核種によって、フォノンのダイナミクスと超伝導を担う電子の振る舞いを選択的に観測していたことになる。サイト選択性というNMRの利点が生かされた好例である。
通常フォノンによる核磁気緩和は、2フォノン・ラマン散乱を伴う過程が支配的で、温度と共に単調に増加し高温でT2に比例する。ではカリウム核で観測された異常な温度依存性はどのように説明できるか?我々は低い特性周波数と非調和性を有するラットリングの特徴として、シャープな固有モードが存在しにくく、温度上昇によって強いダンピングを受けるのではないかと考えた。フォノンのスペクトル幅が広がれば、MHz領域にあるNMR周波数における揺らぎのスペクトル強度が直接緩和率に寄与する(直接過程)と予想される。そこで、温度と共に増大するダンピングを仮定して緩和率の温度依存性を説明した。結局、最初に論文を投稿してから新しい論文が出版されるまでに一年以上が経過した[11]。
しかしまだ話は終わりではなかった。我々のシナリオでは、低エネルギーのラットリングモードは常温付近で過減衰の状態にあり、中性子やラマン散乱のピークとしては観測されないと予想していたが、実際には、その後廣田研やILLで行われた中性子実験で孤立イオンモードとおぼしき非弾性ピークが観測された。更に、前物性研所長の上田和夫氏がこの問題に興味を持ち、2007年に客員所員として物性研に滞在していたドイツTubingen大のThomas Dahm氏と一緒に、ラットリングによる核磁気緩和率を理論的に考察した。Dahm-上田はポテンシャルの非調和性と電子格子相互作用によるフォノン周波数の繰り込み効果を取り入れた簡単なモデルを用いて、2フォノン・ラマン散乱の範囲内でカリウムサイトの緩和率の異常な温度依存性を再現することに成功した[12]。同じモデルで電気抵抗率の温度依存性も自然に再現されており、ラットリングの本質を理解する上で有益な方向を示した理論であると思う。結局、我々の解釈は見当違いであったわけだが、実験と理論が密接に結びついて本質的な進展が得られたという意味では貴重な体験であった。
4.f電子系の多極子秩序
希土類・アクチナイドなどのf電子系化合物において、通常の磁気秩序(磁気双極子の秩序)以外の電気四極子や磁気八極子などの高次の多重極モーメントが示す秩序状態が重要な研究テーマとなっている。これらの多極子が符号を変えながら並んだ反強秩序状態は、実験的な検出が困難であるためにしばしば「隠れた秩序」と呼ばれる。電気四極子はd電子系の軌道自由度に類似の概念であるが、スピン軌道結合の強いf電子系においては全角運動量Jの2次式として表される。同様に磁気八極子、電気十六極子はJの3次式、4次式で表される。このような高次の多極子を直感的にイメージするのは難しいが、多少厳密さを犠牲にすれば、例えば磁気モーメントがゼロでも八極子の期待値が有限である状態とは、スピン密度の全空間での積分値がゼロであっても局所的スピン密度分布が有限であるような状態であると考えてよい。例として図5にJxJyJzで表される八極子に対応するスピン密度分布を示す。(矢印はそれぞれの場所におけるスピン偏極の向きを示す。)スピン密度の積分値はゼロなので、このような秩序パラメータは通常の磁気測定では検出できない。しかしフェルミ接触相互作用を通じて原子核スピンに働く超微細磁場は、原子核の位置における局所的なスピン密度に比例するので、NMRによる検出が可能である。例えば図5に示した例で、中心に希土類イオンがあり、そこから[111]及びこれと等価な方向へ等しい距離に8個のリガンドサイトがある系を考えると、これらのリガンドの原子核スピンは向きの異なる内部磁場を感じるので、NMR共鳴線が分裂するはずである。
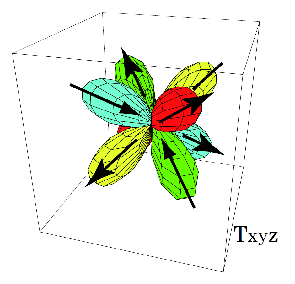
図5 磁気8極子の例
酒井治、椎名亮輔、斯波弘行、Peter Thalmeierの4氏は1997年にこのような機構を初めて提唱し[13]、学位論文のテーマとして1982年に私が行ったCeB6のホウ素サイトのNMR実験から得られたスペクトルが、反強四極子秩序状態に磁場を加えて誘起される磁気八極子によって説明されることを明らかにした。実は学位論文の中で、私は通常の双極子磁場でNMRの結果を説明しようと苦心したあげく、3つの波数成分の重ね合わせからなる如何にも人工的な反強磁性構造を提案したのだが[14]、その後中性子回折の実験によってそのようなスピン構造が否定され、NMRの結果をどう説明するかは未解決であった。この謎を見事に解明した酒井氏らのおかげで、大学院時代の私の実験も15年ぶりに日の目を見ることができた。酒井氏らの解析法は結晶の対称性に基づいて核スピンと多極子の結合の表式を現象論的に求め、多極子秩序のタイプを仮定したときに、外部磁場の下でどのような超微細磁場が生じるかを群論的に考察する方法で、物質によらない一般性を持っている。
その後最近になって、充填スクッテルダイト構造を持つ希土類化合物において隠れた秩序が関与すると思われる相転移が見つかった。我々は首都大の佐藤英行氏、菅原仁氏からPrFe4P12の純良な単結晶を頂いて、PサイトのNMRを行った(菊地淳)。この物質は6.5K以下で明確な相転移を示すが、磁気秩序は検出されていない。磁場と共に転移温度は減少、7テスラ以上で相転移は消滅し、高磁場では重い電子状態が実現する。高温の結晶構造は体心立方であるが、低温相では(1,0,0)の波数を持つ超格子反射が観測され、(1/2,1/2,1/2)の併進対称性が失われた単純立方に変化している。我々がNMRを始めた当初は、この相転移は(1,0,0)の波数を持つ反強四極子秩序であろうという考えが優性であった。図6に示すように、12個の等価なリン原子が一つのPrサイトを囲むように配置されている。これは希土類原子の周囲に局所スピン密度を検出するプローブが網の目のようにめぐらされた構造で、多極子の状態を知るのに非常に好都合であるように見える。実験を始めて間もなく、高温相で観測されたNMR共鳴線のそれぞれが転移温度以下で2本に分裂することが分かった。それぞれのサイトの分裂幅の磁場方位依存性を図7に示す。またこの分裂幅は低磁場では磁場に比例してゼロに向かうことから、ゼロ磁場での秩序パラメータは電気的多極子(Jの偶数次)であり、NMRラインの分裂は磁場によって誘起された磁気多極子によると推定された。
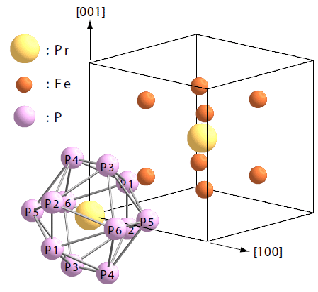
図6 PrFe4P12の結晶構造。
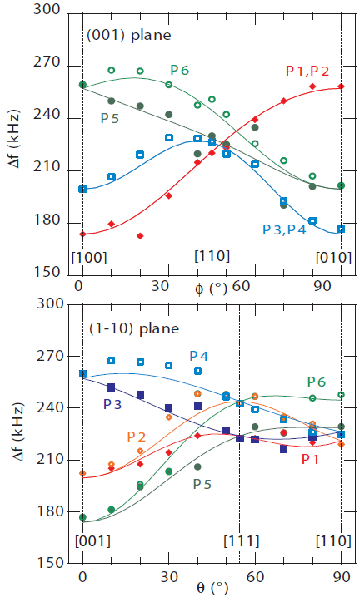
図7 低温相におけるNMR共鳴線分裂幅の角度依存性。
詳細なNMRデータを得た菊地氏は、酒井治氏と椎名亮輔氏のお知恵を借りながら、実験で得られた角度依存性を解析して多極子秩序(最初は四極子秩序と考えていた)を同定しようと試みた。実験結果の重要な特徴は、低温相のNMR共鳴線の数は磁場の方向によらず常に高温相の2倍である、という点である。これは格子の併進対称性を破る反強的秩序によって、Prの周りのP12のケージも2種類に分かれたことで説明がつく。詳細は原論文[15,16]や解説[17]に譲るが、それ以上の分裂がないことは、Prサイトの点対称性が低温相でも低下していないことを意味する。即ち、二つの副格子上のPrは異なる4f電子の電荷分布を持つが、いずれも点群Thの対称性を保つような電荷分布でなければならない。これは秩序パラメータが点群の対称操作に関して不変である、即ち恒等表現に属するということと同等である。このような秩序パラメータは、四極子からは作ることは出来ない。群論的な考察から全対称な秩序パラメータは十六極子、または六十四極子に限られることが分かった。Th群に関して不変な電荷分布を持つ多極子の例(Jx4+Jy4+Jz4-3/5で表される十六極子)を図8に示す。我々の論文以前にKiss-倉本は磁化の異方性や我々のNMRの結果に基づいて、スカラー秩序パラメータを提唱した[18]。またFeをRuで置き換えたPrRu4P12は160Kという高い温度でQ=(1,0,0)の超周期構造を伴う金属絶縁体転移を示すが、瀧本はPrRu4P12の低温相が図8に示される十六極子の反強秩序相であると提唱した[19]。複数の研究者が独立に同様な結論に到達したので、この秩序状態には「全対称秩序」、「スカラー秩序」、「十六極子秩序」「モノポール」など異なる名称がつけられている。
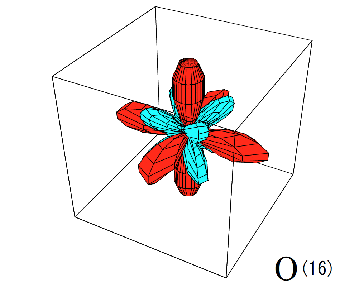
図8 全対称な電気多極子(十六極子)の例。
では、何故このような高次の多極子の秩序状態が生じるのか?これに関しては播磨尚朝氏(神戸大)が多極子と伝導電子の相互作用に起因するフェルミ面の不安定性という機構を提唱している。この系の伝導バンドは主にリンのp軌道で作られるP12ケージ上のxyz対称性を持つ分子軌道から成り立っており、フェルミ面は(1,0,0)方向にネスティングを示す。ケージの中心にいるf電子と伝導電子の間のクーロン相互作用のために、伝導電子の感じるポテンシャルはf電子系の電荷分布に敏感に依存する。従ってf電子の電荷分布に(1,0,0)の波数の反強秩序が生じれば、伝導電子のポテンシャルに同じ波数の変調が加わり、フェルミ面に部分的なギャップが生じエネルギーが安定化される。これはよく知られたパイエルス転移と同様の機構である。通常のパイエルス転移において格子が果たす役割を、f電子の多極子が果たしていると言えよう。ここで重要なのは、伝導電子のポテンシャルに影響を与えるのは、結晶のサイト対称性を保持するような電荷分布に限られるという点であり、秩序パラメータが全対称である必然性が理解できる。
5.その他のテーマ
大部長くなってきたので、上記以外の主なテーマについて簡単にまとめておこう。
I.2次元スピン系 (CuCl)LaNb2O7:イオン交換法というソフト化学的手法によって合成されたこの物質は、シングレット基底状態を持ち24Kの励起ギャップを示す。最初は理論的に強い興味が持たれている正方格子上のJ1-J2モデルの具体例かと思われたが、我々のNMR実験から局所的な構造変調が磁性に重要な影響を与え、J1-J2モデルは当てはまらないことが分かった(尾形誠之、吉田誠、試料は陰山洋氏)[20]。ギャップが消失する磁場が励起ギャップに比べて異常に小さいことから、エキゾチックな磁場誘起相の出現に興味が持たれる。
II.鉄フタロシアニン錯体 TPP[Fe(Pc)(CN)2]2 :この物質は、縮退したd軌道にスピンを持つ鉄イオンが、環状フタロシアニン分子の中心に配位することで、イジング局在スピンと伝導パイ電子が強く結合したユニークな擬1次元伝導体で、数年前に物性研の田島研究室で巨大負磁気抵抗効果が発見された。2年前から鉄に結合したシアノ基中の13C核や15N核のNMRを行っており(原洋太、永島裕樹)異方性の強い反強磁性秩序を観測した。現在パイ電子の振る舞いを調べるためにフタロシアニン環上の炭素を13Cで置換した試料の合成を田島研の松田助教にお願いしているところである。
III.金属絶縁体転移を示すパイロクロア、スピネル酸化物:パイロクロア格子上に局在スピンを持つ反強磁性体の多くは、強いフラストレーションのため低温まで長距離秩序を示さない。しかし最近温度によって金属―絶縁体転移を示すパイロクロア/スピネル酸化物が見つかり、Hg2Ru2O7、Cd2Os2O7、LiRh2O4などについてNMRの実験を行っている(吉田誠、和気剛、永島裕樹)。Hg2Ru2O7(Cd2Os2O7)においては160K(240K)での金属―絶縁体転移と同時にコメンシュレートな磁気秩序(インコメンシュレートなSDW)が発生し、また混合原子価を持つLiRh2O4では絶縁体相で電荷秩序を起こすと同時に3000Kもの大きな結合エネルギーを持つシングレット・ダイマーを形成する。同じパイロクロア格子上の絶縁体であっても、金属―絶縁体転移に近い系の振る舞いは局在スピン系と大きく異なり、多彩な秩序状態を示す(新領域高木研、物性研廣井研との共同研究)。
IV. 鉄砒素系超伝導体:鉄と砒素からなる2次元層を含む物質群で、今年2月に26Kの超伝導転移温度が発表されるや次々と記録が更新され、1月余り後には転移温度は50Kを超えた。高温超伝導ブームの再現かという声も聞こえるが、我々も、今年新しくお隣同士となった大串研から試料を頂いて、実験を始めたところである(北川健太郎)。
この他にも、ここに紹介しきれないテーマで多くの実験を行ってきた。その中にはまだ論文として発表されていないものも多く、共同研究者の方には大変ご迷惑をおかけしている。これはひとえに私の怠慢のせいであるが、最近は吉田誠助教の叱咤激励のおかげで、少しずつ改善されている(と思う)。また、数は少ないが物性研の共同利用制度を通じた共同研究も行っており、その中には私の研究テーマとはかけ離れたものも含まれている。例えば、物性研の八木研究室を通じて紹介された奥地拓生氏(名古屋大)はNMR用に開発したダイアモンド・アンビルセルを用いて高圧下の氷に吸蔵された水素のダイナミクスを調べた。また鈴木義茂氏(大阪大)は、トンネル磁気抵抗効果を示すコバルト微粒子と有機物のコンポジット材料に対して、NMRを用いてコバルト微粒子中のスピン偏極分布を測定した。このような共同研究を通して普段聞くことのない研究テーマについて知る機会を得ることは、我々にとっても貴重な経験である。
6.装置と技術開発
NMRの信号が初めて観測されたのは、第2次大戦終結直後である。それから60年余りを経て、今やNMRは化学、生物、医学、材料科学など自然科学の殆どすべての分野で活用されており、特に生物・医学への応用には目覚しい進展がある。物理分野でも、単一スピン検出を目指す力学的検出法の開発や、2次元電子系の特徴を利用した電気抵抗による核スピン共鳴の検出法など、革新的な技術が生み出されている一方で、我々が興味をもっている物質科学に関しては、技術的にほぼ完成し近い将来大きな変化があるとは思えない。実験技術という点では、強相関電子系や量子スピン系の研究においては新奇な量子状態を実現するための舞台づくり(強磁場、低温、高圧などの極限環境)がむしろ重要である。このうち強磁場に関しては、18テスラまでは物性研の超伝導マグネットでカバーでき、より高磁場が必要なときはグルノーブル強磁場施設にて旧知の友人であるClaude Berthier、Mladen Horvatic両氏と共同研究を行っている。低温については吉田助教の努力で20mKまでの測定が困難なく行えるようになった。研究室で開発した装置として、超伝導マグネット中で単結晶試料の方位を制御できるNMR用ゴニオメータと、高圧実験用の圧力セルを紹介したい。
これまで紹介した研究例からも分かるように、サイト選択性というNMRの利点を最大限に発揮するには、単結晶試料用に対する精密な角度分解スペクトルが必要とされる場合が多い。私は以前から超伝導マグネット中で試料の方位を任意に設定できるNMRプローブの必要性を感じていた。物性研に着任後、現所長の家泰弘氏から低温実験に使われていたコンパクトな2軸ゴニオメータを見せて頂き、それを元に新物質科学部門所属であった山崎技官(現工作室所属)がNMRプローブを設計した。約0.2度の制御が可能なこのプローブは、単結晶試料を用いた全ての実験に使われ大きな威力を発揮している(図9左)。このプローブの設計図は国内の幾つかのNMRグループにも提供されている。このようなささやかな貢献も、全国共同利用研究所に籍を置く者の務めであろうと思っている。
今日の物性研究では磁場と並んで圧力も必要不可欠な手段である。我々も数年前に物性研の上床美也氏と物材機構の松本武彦氏の協力を得て、NiCrAl合金を用いたピストン・シリンダー型の圧力セルを設計し(新井浩一)3GPaまでの高圧下NMRを可能にした。この圧力セルは上に述べた2軸試料回転台に載せることが出きるので(図9中央)高圧下で単結晶試料の方位を制御した測定が可能である。その後更に高圧を目指して、昨年度から研究室に加わった北川健太郎氏(学振PD)が八木研究室と上床研究室と共同で対向アンビル型のNMR用圧力セルを開発している(図9右)。3ヶ月の間に何と40種類以上(!)もの様々な形状のガスケットを試作して最適化を目指した結果、ダイアモンド・アンビルセルに類似の構造で、5立方ミリメータという大きな試料体積を保ちながら8GPaの圧力を発生することに成功した。現在は、液体アルゴンを圧媒体に用いて高い静水圧性を実現するとともに、2軸試料回転機構や希釈冷凍機と組み合わせることにチャレンジしている。

図9 (左) 試料回転用2軸ゴニオメータを備えたNMRプローブ。(中央) 2軸ゴニオメータにセットされたピストン・シリンダー型圧力セル。(右) 現在開発中の対向アンビル型圧力セルと2軸回転機構。
7.おわりに
予定の紙数を大分オーバーしてしまった。振り返ってみると柏移転後8年の間、色々なテーマに見境なく手を出してきたという感じがする。分野が広がりすぎて、多少消化不良を起こしているという反省がないわけではない。個々のテーマについて私自身が表面的にしか理解していないために、本当に面白い展開を見逃しているのではないかという気もする。年をとって、実験データの解析や新しいテーマの勉強が以前ほどスピーディーに出来なくなっていることにも、原因があるかも知れない。しかし面白そうなテーマが目の前にあれば、やはり手を出さずにはいられない。良かれ悪しかれ、消化不良とは分かりつつもこのようなスタイルで今後も研究を続けていくであろう。そのうち腰を落ち着けて集中できるライフワークとなるべきテーマが見つかるかも知れない。多少油切れの兆候がある私の至らなさを補っているのは、研究室の若いメンバーの熱意である。継続的に若いメンバーが入れ替わり、新しい空気を吹き込んでくれたおかげで、今までやってこれたのだと思う。最後に、これまで多くの貴重な試料を提供下さり、また日々の議論を通じて様々な問題の理解を助けて頂いた共同研究者の方々にお礼を申し上げて、稿を閉じたいと思う。
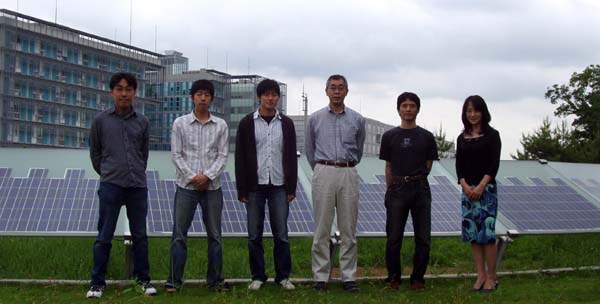
今年度の研究室のメンバー。向かって左より吉田誠(助教)、小山幸紀(M2)、永島裕樹(M2),筆者、北川健太郎(学振PD),川井明子(秘書)の諸氏。
参考文献:
[1] H. Kageyama et al., Phys. Rev. Lett. 82 (1999) 3168, K. Onizuka et al., J. Phys. Soc. Jpn. 69 (2000) 1016.
[2] K. Kodama et al., Science 298 (2002) 395.
[3] M. Takigawa et al., Phys. Rev. Lett. 101 (2008) in press.
[4] F. Levy et al., EPL 81 (2008) 67004.
[5] K. Kodama et al., J. Phys.:Condens. Matter 17 (2005) L61.
[6] T. Waki et al., J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007) 073710.
[7] M. Hanawa et al., Phys. Rev. Lett. 87 (2001) 187001, H. Sakai et al., J. Phys. Cond. Mat. 13 (2001) L785.
[8] O. Vyaselev et al,. Phys. Rev. Lett. 89 (2002) 017001.
[9] K. Arai et al., J. Phys.:Condens. Matter 14 (2002) L461.
[10] S. Yonezawa, Y. Muraoka, Y. Matsushita, and Z. Hiroi, J. Phys.:Condens. Matter 16 (2004) L9-L12.
[11] M. Yoshida et al,. Phys. Rev. Lett. 98 (2007) 197002.
[12] T. Dahm and K. Ueda, Phys. Rev. Lett. 99 (2007) 187003.
[13] O. Sakai, R. Shiina, H. Shiba, and P. Thalmeier, J. Phys. Soc. Jpn. 66 (1977) 3005.
[14] M. Takigawa, H. Yasuoka, T. Tanaka, and Y. Ishizawa, J. Phys. Soc. Jpn. 52 (1983) 728.
[15] J. Kikuchi, M. Takigawa, H. Sato, and H. Sugawara, J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007) 043705.
[16] O. Sakai et al., J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007) 024710.
[17] 酒井治、菊地淳、椎名亮輔、瀧川仁、日本物理学会誌 63 (2008) 427.
[18] A. Kiss and Y. Kuramoto, J. Phys. Soc. Jpn. 75 (2006) 103704.
[19] T. Takimoto, J. Phys. Soc. Jpn. 75 (2006) 034714.
[20] M. Yoshida et al., J. Phys. Soc. Jpn. 76 (2007) 104703.